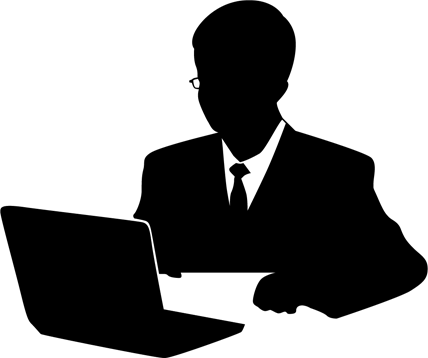社宅の賃料値上げは仕方ない?交渉の余地はあるのか

社宅の賃料が値上げされると、従業員の家計への影響だけではなく、会社の負担も避けられません。しかしすぐに「値上げは仕方ない」と諦めるのではなく、オーナーと交渉してみるのも有効な手段です。本記事では、社宅賃料の値上げに直面した際の背景や対策、交渉のポイントについてくわしく解説します。
社宅の賃料値上げが起こる理由
社宅の賃料値上げの背景には、いくつかの要因があります。まず、現在の物価上昇にともない、オーナー側の管理費や人件費も増加しており、増えたコストを賃料に反映する動きが広がっています。
また、円安や海外投資家の関心が高まるなかで、不動産価格が上昇し、とくに都市部では地域全体の価値が高騰しています。さらに、大企業を中心とした賃上げの影響で「給与が上がれば賃料を引き上げても問題ない」との見方が広がっている点も要因です。
物価高騰や賃上げの流れから周辺の賃料相場が上昇し、社宅の賃料にも値上げの圧力が及んでいます。結果として、従業員の負担が増え、会社や個人にとって賃料交渉が一層重要な課題となっています。
賃料の値上げ交渉には必ず応じなければいけないのか
賃貸契約における賃料の値上げ交渉は、法律上必ず応じなければならないものではありません。そもそも賃料には、契約当初に設定される新規賃料と、契約継続中に改定される継続賃料があります。
値上げ交渉は継続賃料に該当し、双方の合意がなければ成立しません。前項で先述したとおり、賃料改定は、土地価格や物価の上昇により、現在の契約賃料と新規賃料との間に乖離が生じる場合に行われます。
しかし、貸主からの値上げ要請に対して借主が合意しなければ、値上げは成立しません。もし貸主が一方的に新賃料を適用していた場合、速やかに指摘し管理会社やオーナーと交渉を行う必要があります。
もし値上げ提案に対して合意できる場合は、双方が納得する水準で新たに合意更新が行われます。一方で、値上げ幅に合意できない場合は、交渉を継続しつつ、契約更新日を迎えた場合には、現行の賃料で自動更新される法定更新となります。
借主が旧賃料を支払い続けることで、家賃を支払う意思を示せば法的に保護されます。ただし、法定更新には貸主との関係悪化や企業イメージへの影響などのリスクがともなうため、円満な合意を目指す必要があります。
賃貸契約は双方の合意をもとに成り立つため、値上げ交渉があった場合でも、冷静に対応し、自分の立場を守らなければなりません。
賃料の値上げについて交渉の余地はある?
賃料値上げの打診がきたときに、すぐに「いいですよ!」と応じられる方はあまり多くないでしょう。まずは「これまでと同額ではないと厳しい」と貸主に伝え、現状維持を試みましょう。オーナーも空室による家賃収入の減少を避けたいと考えているため、交渉の余地は十分にあります。
しかし、実際は賃料据え置きが難しい場合は「+⚪︎⚪︎円ではどうでしょうか」と、値上げ幅を減らす提案をすると効果的です。少ない値上げ幅で交渉がまとまれば、オーナーは少額でも値上げが実現し、借主側も負担を抑えられるため、双方にとってよい結果が得られます。
一方で、交渉に無理がある場合は、撤退も視野に入れる必要があります。契約上の立場では貸主が強いため、無理に交渉を続けると、契約更新を拒否されるリスクがあるからです。
また、交渉相手の多くは不動産管理会社です。彼らは賃料交渉に慣れており、交渉に慣れていない人にとっては精神的負担や時間の消耗が避けられません。多忙な時期は、消耗を避けるため先方の言い値で妥協してしまいたくなりますが、社宅代行会社に交渉を任せるのもひとつの方法です。
不動産業界や賃貸仲介にくわしい会社であれば、より効果的に交渉を進めてくれる可能性があります。ただし、代行会社を利用しても必ずしも賃料が据え置きになるわけではありません。
物価高やオーナーの事情も考慮する必要があるため、最終的には値上げ額を抑える結果となる場合もあります。外部に任せて自身の負担を軽減し、交渉が失敗しても「プロがやってダメなら仕方ない」と納得しやすくなるのもメリットです。
まとめ
物価高騰や賃上げの影響により賃貸物件の賃料値上げが起こっていますが、社宅の賃料値上げは、会社にとっても従業員にとっても負担になります。しかし必ずしも賃料の値上げに応じないといけないわけではなく、交渉次第で賃料の据え置きや値上げ幅を抑えられる可能性があります。現実的な着地点を見つけつつ、ストレスの少ない交渉を目指しましょう。